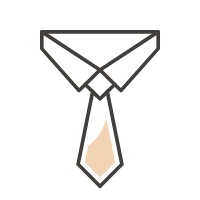 人事労務相談
人事労務相談
 人事評価
人事評価
【社員の不満や不公平感をなくす人事評価とは?】
Ⅰ 失敗しがちな人事評価、業績評価の方法
6月が過ぎ7月に入り、多くの企業で賞与が支給されました。
社員は賞与額に目が行きがちではありますが、事業主や所属長にとっては苦労して部下を評価した結果・あかしです。この結果には、下期も目標に向けて頑張ってほしいとの願いも込められています。
この人事評価ですが「公正な尺度」で、「明確な基準」で、社員を評価することができていますか。
「当社は明確な基準で評価している」
「公正なルールにのっとって社員の順位付けができている」
といえる組織は、少ないのではないでしょうか。
実際には、
- 評価はだいだいの印象で付けている
- 最後は社長の好き嫌いの評価になっている
今まではこの方法でも“良かった”のかもしれません。
しかし、これは、“たまたま、良かった”と考えなくてはいけません。
現在の自社における環境・状況を改めて見てください。
このような“アバウト”な評価をされては納得感ゼロであり、公正な評価をされていないと感じる優秀な社員はどのように思うでしょうか?
このように、“だいたいの印象で評価”している 企業は、今すぐ変わりましょう。
みなさんの企業におられる若くて優秀な人材が希望をもって働ける環境にするために。
それでは、公平で明確な評価を行うために、どのような評価の仕組みを構築すればよいのでしょうか。
Ⅱ 公平な評価を行うためには?
~明確な順位付けが可能な仕組みを構築しましょう~
社員が感じる、“公平と感じることができる人事考課”とはどのようなものでしょうか。
それは、
- 明確な行動目標
- 定量化された個別目標
- 質的かつ量的に数値化され統一が図られた評価基準
- 評価者によってブレのない評価結果
このような、“公平と感じることができる人事考課”を行うためには、以下の基準を設けた仕組み作りを目指します。
- 定量的かつ具体的な組織目標
- 組織目標達成に必要とされる明確な行動目標・計画
- 質的かつ量的に数値化され、全社的に統一が図られた評価基準
- 頑張り、貢献度及びプロセスなど、定量化が困難な項目を評価するルールの設定
以上の仕組みを設定し運用することで明確に
- 社員間の順位付けを行い
- 客観性ならびに公平性を担保した評価
なお、(4)のような評価に関し定量化が困難な測定項目については、以下のようなルール(例)を設けて評価します。
頑張り、貢献度及びプロセスに対する評価(運用例)
- 3年連続A評価の場合、全体の人事評価に+1加点する
- A=優れた頑張りを発揮(顧客から特に賞賛される)
- B=期待どおり (顧客満足が想定どおり)
- C=不十分・不足 (トラブルあり、謝罪等実施)
明確な順位付けによってもたらされる効果
- 目指すべき姿としては、組織ごとに1位から100位まで明確に順位付け可能な仕組みとする
- 下位評価者(71~100位の下位3割)については、しかるべきフォローをすることでウイークポイント改善のチャンスととらえる
- 明確な評価の運用により、ウイークポイントの洗い出しが可能となる
- ウイークポイントの洗い出しにより、集中的かつ効果的なフォローが期待できる
- 下位層のウイークポイントが改善されると社員全体におけるレベルの底上げが図られる
Ⅲ 不満や不公平感をなくす人事評価 ポイント5つ
実際には、各社に合わせて個別具体的に評価の仕組みを検討していくことになりますが、共通して注意すべき事項として、以下5つのポイントがあります。
-
注意ポイント:評価基準があいまいにならないこと対応方法 :評価方法や評価項目の明確化
-
注意ポイント:評価者によって評価結果のばらつきをださないこと対応方法 :評価者研修の実施
-
注意ポイント:評価結果のフィードバックや説明が不十分となるなど納得感がない状態を防止すること対応方法 :評価基準の定量化
-
注意ポイント:評価結果が昇進に結びつく仕組み作りとすること対応方法 :反映方法の明確化
-
注意ポイント:頑張りに対する評価や達成までのプロセスを明確に評価できる仕組みとすること対応方法 :評価するためのチェックシートや各種評価ツールの導入
Ⅳ 組織の目指すべき姿とは! なぜ人事評価を行うのか、意識することの重要性
自社において人事評価を行う理由はどうしてでしょうか?
おそらく、“〇〇を達成するため” “▲▲まで成長・拡大を図るため”等 明確な理由が存在し、そのための今期目標を掲げていることから、人材育成、人事評価を行っているはずです。
目標に向かって日々意思決定する時、常に「何のためにこの意思決定を行う必要があるのか?」
意識して行動すると、その後の結果が見違えるように向上します。また、意思決定に迷った時も「この意思決定の目的は何であるか?」を自分に問いてみます。すると、自然と方向性がみえてきます。
人を評価する際や重要事項の決定をする時に、
- 「何のために行うのか?」
- 「意思決定の目的は何であるか?」
ぜひ、簡単な形で結構ですので整理してみましょう。
【例えば】
- 自社の目標
- 会社のスケール拡大(売上及び利益)
- 拡大のため、人材の質ならびに職務遂行マインドの向上
- 人材の質ならびにマインド向上の持続化を図るため、社員ごとに見合う
メリハリのある処遇および賃金分配を図りたい - メリハリのある処遇および賃金分配を実現するため、明確な評価の仕組みを構築したい
Ⅴ 結論
今すぐ、社長の好き嫌いで行う人事評価・業績評価から卒業しましょう。
聞き分けが良くフットワークも軽い働き者で有能な若手社員からいなくなってしまいます。
最近よく使われる言葉で「コスパ」というものがあります。
余り個人的には好きではない言葉ですが、まさに「コスパが悪い」などと判断されたあかつきには、どれほど社員の就業意欲低下をもたらすことでしょうか。
- 自分の組織は大丈夫
- 職場を好きな社員が多い
と感じている組織ほど至急、現状を検証してください。
そして、「不明確な順位付け」、「不公平・不明瞭な評価制度」が判明したら、
できることから、基準の明確化、公平性のある順位付け の仕組みに改善し、
公明正大な社員マネジメント、組織コミュニケーションを図っていきましょう。
組織運営で重要なことは、「マネジメントとコミュニケーション」です。
永遠の課題であります。
もし、お困りのことがございましたら ぜひ、あんしんサポートへご連絡ください。
Contact usお問い合わせ
お問い合わせ・ご相談につきましては、すべて無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
-
お電話でのお問い合わせ
 03-5419-4222
03-5419-4222
受付時間:平日10:00-18:00
-
メールでのお問い合わせ
 お問い合わせ
お問い合わせ
受付時間:24時間受付
 社会保険労務士法人 あんしんサポート
社会保険労務士法人 あんしんサポート